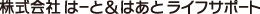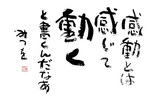初めまして。
昨年4月からデイサービス管理栄養士として勤務しております、冨林かおり と申します。
利用者様の食のお困りごとについてお聞きしたり、栄養計画を立てたり、デイサービスの食数・発注管理をしたり、行事食や行事おやつを考えています。
また、生活相談員、介護士、看護師、リハビリスタッフ、歯科衛生士とこまめに情報交換して、利用者様一人ひとりに合った食事方法を提案しています。
では実際、
その情報交換が
どんな風に活きてくるかというと...
【口腔・嚥下機能の観察】
入れ歯が安定していない
→食事形態の見直しと入れ歯安定のための処置が必要では?
【浮腫(むくみ)状態の観察】
ここ最近ふくらはぎや足首がむくんでいる
→その方の体重増減の原因を精査してから栄養計画を立てます
【認知面の観察】
お箸の使い方が分からないために食事動作が止まっている、最近ほかにも認知症症状が見受けられる
→ 職員がこまめにお声がけや一部介助に入る、それでもお箸が使えなければ自助スプーンをご用意してみる
【心の問題・生活状況】
うつ傾向、自宅での清潔管理は行き届いていない、家族様は遠方におりなかなか自宅の様子を見にこれない
→自宅での食事状況を再確認。うつ症状による食欲低下や過食症状は出ていないか?自力で食事の準備ができないのであれば何かお届けできる商品はないか?
【運動機能の観察】
右に麻痺があり左手左脚しかうまく動かせない
→左手だけでも食事動作を取りやすい自助箸・自助食器の準備、食事姿勢をクッションなどで整えて体軸まっすぐの状態で食事をしていただく
--------
などなど。
これらは全部、他職種スタッフから情報をもらったりアドバイスをもらいながら実践していることです。
はあとのデイでは、全てのスタッフが介護業務(軽介助)に入ります。もちろん、介護スタッフから指導をしっかり受けた上ですが、時にはトイレ介助に入ることも。
介護を通じて、利用者様の状況を肌で感じられます。
この距離感でケアができることを活かし、どの職種もプランを立てています。
わたしは、前職でも特養やデイサービスの管理栄養士業務をしていましたが、ここまで現場の介護業務に入ったことはありませんでした。
はあとのデイサービスで働くようになってからは、これまで気づかなかった利用者様の変化にも気付くようになりました(^^)
食事を安全に美味しく食べていただくには、
たくさんの小さな『気づき』が必要です。
利用者様に、
心も体も元気に過ごしていただけますように
これからも頑張ります(^^)♪
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
写真は3月中旬に実施した
『春の手づくりおやつレク』の様子です。
利用者様には皮を焼いてもらったり、餡子を丸めてもらったり、薄ピンク色のモチっとした皮で餡子を包んでもらったり...


桜餅(関東風)の出来上がり!

簡単に作れますし、味も良く、大好評でした♪手作りしながら昔を思い出していた方もおられました(^^)
五感を呼び覚まし、楽しく、機能維持!
また何か考えて実施したいと思います。