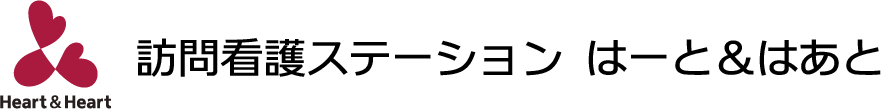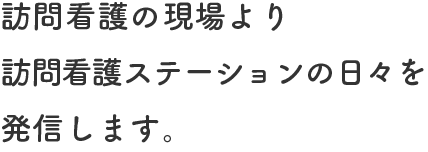私はお笑いが好きで、テレビでバラエティ番組やお笑いの賞番組をよく見ます。(今はテレビで見られなくても、スマホで見逃し配信があるので、とても便利です。)昔から笑うと健康に良いって聞きますよね。
『笑う門には福来たる』とも言いますし、笑うことってとても大切だと思います。
しかし具体的にどんな効果があるのだろうと調べたら、大阪府が2003年に笑いが健康に及ぼす影響について掲載していました(もう20年程前!)。
その内容とは、ガン細胞を攻撃するNK(ナチュラルキラー)細胞が笑うことにより活性化され、ガンを抑制する働きがあるということです。糖尿病の方は、笑うとストレスが軽減され、血糖値の上昇抑制にも効果があるとのこと。もちろん体を動かすと有酸素運動にもなるので、ダイエットにも良いそうですよ。
笑うと健康にとても良いということですね。
 1995年にはインドの内科医が『笑いヨガ』というものを考案し、笑いの体操とヨガの呼吸を組み合わせた健康法もあります。笑いながら体操をすると、有酸素運動になり免疫力アップ、ストレスも解消されるということです!日本では2006年頃から広まり、今や世界100カ国以上でされています。
1995年にはインドの内科医が『笑いヨガ』というものを考案し、笑いの体操とヨガの呼吸を組み合わせた健康法もあります。笑いながら体操をすると、有酸素運動になり免疫力アップ、ストレスも解消されるということです!日本では2006年頃から広まり、今や世界100カ国以上でされています。
体操法を見てみると、まずは「わっはっはー、わっはっはー」と無理やり笑うことから始めても効果があるそうです!笑そしてみんなでテーマを決めて猫のポーズをとりながら笑ったり、ゴリラのポーズをとりながら笑ったりとやり方は様々です。
参加されている方のインタビューもありましたが「初めは変な集団と思いましたし、抵抗もありながらイヤイヤ参加しましたが、続けていたら目覚めも良いし体がスッと軽くなっている感じもして効果を実感出来たので、今も続けています!」と仰っていました。
(集団で一緒に参加する時は、ちょっと勇気が必要かも笑)
大阪府が掲載していた『笑いと健康』の記事には、応募の中からいくつか身近で起こった【おもろい話】も載っています。
では、最後に私も【おもろい話】
妻から聞いた話で、20年前くらいの話です。
ある日、地域の避難訓練があったそうです。それを聞いたおばあちゃんが「ガスの元栓は閉めてあるか?水道は大丈夫か?」と家族にあれこれ指示を出しながら本人は座って何かゴソゴソとしていたそうです。
いざ公民館に避難する時におばあちゃんはカバンを肩から掛けており、中身を見ると1人分だけの食料が入っていたそうです!
そんなおばあちゃんは今年で100歳になり今も元気に過ごしています。
初めまして、4月から訪問看護ステーションはーと&はあとで働くことになりました看護師の新地啓子と申します。今年で看護師になり17年になります。これまで、回復期リハビリ病棟や脳神経外科病棟、そして緩和ケア病棟で働いてきました。
脳神経外科病棟で働いていた際、ある患者様のお看取りをさせていただきました。それまで静かに患者様を囲っていたご家族様でしたが、私が声をかけると、堰を切ったようにみなさん泣き出し、口々に思いを吐き出されました。思い出話をたくさんされ、ご家族みんな泣き笑いしながらの賑やかなお看取りとなりました。その時に、看護師の関わり方次第で、こんなに温かいお看取りが出来るんだと感じました。この出来事をきっかけに終末期看護に興味を持ち、緩和ケア病棟に転職しました。
その後、看護師人生の半分以上を緩和ケア病棟で過ごし、「その人らしさ」を常に考え日々の看護を行ってきました。最期のその一瞬まで、どのように生きたいのか、誰とどこでどう過ごしたいのか、患者様やご家族の死生観や価値観は様々です。病気や辛い症状により我慢や制限ばかりの人生ではなく、その人がその人らしくあるために、看護師として何が出来るかを常に考え、専門職として最善を尽くしていきたいと思っております。
訪問看護の経験は初めてですが、利用者様やご家族様にとって、相談しやすく安心感を与えられる様な看護師になりたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。
初めまして。今月入社した、理学療法士の濟城翔一と申します。入職するまでの5年間は、奈良県で過ごしておりました。
これまで回復期病院、クリニック、そして訪問リハビリで勤めてきました。その中でも利用者様の自宅に伺い、ご本人の生活に合わせたサービスが提供できるという点で、訪問リハビリにやりがいを感じております。そのため、今までの理学療法士人生で最長の約5年間、奈良県で訪問リハビリに携わってきました。
私は今までの経験から、自宅での過ごし方が大事だと感じています。病院とは違い、毎日サービスの提供をさせていただく機会が少ないこともあり、頑張って自宅に戻れたものの、生活が上手くいかず、転倒等の理由から再度入院となってしまう方もいらっしゃいました。自宅でより長く生活するために、自主トレーニングメニューの提案をさせていただくほか、移動しやすいよう家族様に家具の配置を相談させていただくこと等もあります。ご本人はもちろん、家族様にもご協力をいただきながら、看護師やケアマネジャーと連携を図り、より良いサービスを提供できるように頑張ります。
まだまだ至らないところもありますが、今までの経験を活かし、少しでも利用者様のお役に立てるよう精進しますので、どうぞよろしくお願いいたします。
皆様お久しぶりです。看護師の徳井です。
月日が経つのは早いもので、入職当時は3歳だった息子はこの春ついに小学生になります。息子は新しいランドセルを背負い、入学式を心待ちにしています。一方、私はまだ寒い日が続いている為、春の陽気を待ちわびています。
さて皆さんは「寒暖差疲労」という言葉をご存知でしょうか。今回は寒暖差が身体に与える影響についてお伝えしようと思います。
1日の気温差が7℃以上になると寒暖差が大きいといいます。寒暖差は私たちの身体にとってストレスとなり、自律神経に大きな負担をかけます。この自律神経への負担が、様々な不調を起こすとされています。
【寒暖差疲労による不調】
➀頭痛やめまい
➁肩こり、冷え性
③体のだるさ
④食欲の低下、下痢、便秘
⑤イライラや不安、落ち込みなどの精神的なダメージ
【寒暖差疲労への対策】
1⃣温度差をなくす
体に寒暖差を感じさせないことが大切です。エアコンを適切に使用し、一定の快適な温度を保ちましょう。外気温との差が大きくなるのを避け、温度差は7℃以下になるようにしましょう。
2⃣バランスのとれた食事を心がける
バランスの良い食事を摂り、寒暖差疲労に負けない体づくりをしましょう。エネルギー源になるたんぱく質や、疲労回復効果のあるビタミンB群を積極的に摂取しましょう。
3⃣良質な睡眠をとる
「交感神経」と「副交感神経」のバランスをとる事も大切です。良質な睡眠は心身の疲労を回復させるために有効的です。
4⃣適度な運動をする
体力が落ちると寒暖差疲労が起きやすいとされています。適度な運動を習慣化して、疲れにくい体を目指しましょう。
5⃣お風呂にゆっくり浸かる
入浴すると全身の血行が良くなり、体に蓄積された疲労物質を取り除く効果が期待できます。ぬるめのお湯にゆっくり浸かるのがおすすめです。
日頃から対策をおこない、寒暖差疲労をため込まないように心がけましょう!
いつもと違う不調を感じた場合は、いつでも看護師にご相談ください。
 1995年にはインドの内科医が『笑いヨガ』というものを考案し、笑いの体操とヨガの呼吸を組み合わせた健康法もあります。笑いながら体操をすると、有酸素運動になり免疫力アップ、ストレスも解消されるということです!日本では2006年頃から広まり、今や世界100カ国以上でされています。
1995年にはインドの内科医が『笑いヨガ』というものを考案し、笑いの体操とヨガの呼吸を組み合わせた健康法もあります。笑いながら体操をすると、有酸素運動になり免疫力アップ、ストレスも解消されるということです!日本では2006年頃から広まり、今や世界100カ国以上でされています。