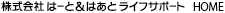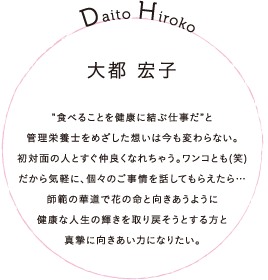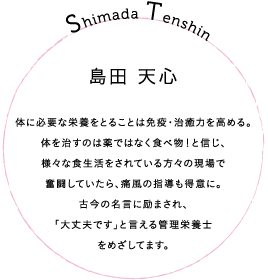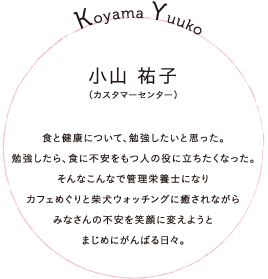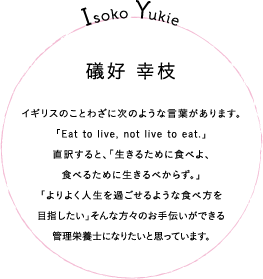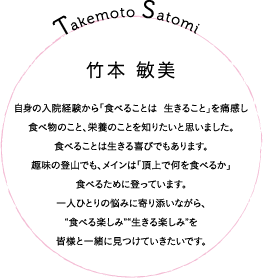こんにちは。京都管理栄養士の島田です。
朝晩は涼しくなってきてきましたが、まだまだ秋の空気は感じませんね。季節の変わり目が年々かわってきているのでしょうか。
さて、先日新規のご相談にお伺いしたT様(80代、男性)
娘様から「現在、入院中で刻みとろみ食を食べていて、退院後も同じ食事を配食してくれるところを探してる。週末には退院なのでお願いしたい」とのご依頼を受け面談に伺いました。病院への訪問はかなわず、自宅への訪問でご家族様にご面会させていただくことに。
お聞きすると、嚥下は問題ないようなのですが、歯の治療をされていて現在はキザミでないと食べられず、とろみをつけて喫食されているようです。
やわらか食のTaBeLu+も形態としてはいけるのかなと思い、健康食のキザミ食、TaBeLu+、軟菜食のキザミ食など、さらにソフト食と、それぞれの形態と特長をご説明させていただきました。
相談の結果、病院の形態に合せていただき、健康食のキザミ食をご用意させていただくことに。自宅にはとろみ剤のご用意がないとのことから、事務所にあるとろみ剤のサンプルを一緒にご用意させていただくことに。
ただ、そこで問題が・・・明日退院なので明日の食事も必要とのこと。(金曜日に訪問に伺いましたが、土曜の午前中に退院予定でした)早くて食事用意ができるのが明後日の日曜になるため土曜の食事をどうするかを改めて相談。
奥様と二人暮らしのT様。普通食なら用意もできるがキザミ食はちょっと・・・ということになり、急遽用意ができるTaBeLu+を土曜日だけご用意させていただくことに。TaBeLu+をお持ちして刻んでからとろみをつけて召し上がっていただくようお願いしました。
さらに、次の問題が、土曜のTaBeLu+の献立が魚料理とカレーでした。カレーはT様苦手で、最初にもってきた食事が苦手なものだと以降配食はいらないと言い出しかねないとご家族様が心配され、できればカレーを変えてほしいと。
カレーをかえることはできず、最終提案でカレーの代わりにソフト食のおかずを1品代用としてお持ちして食事を召し上がっていただくことに。(ソフト食だけでは量が少ない為、補助ゼリーのサンプルもサービスで1個お付けしました)
そのため、ご家族様には、健康食の召し上がり方とお届け案内の説明、TaBeLu+の召し上がり方とお届け案内の説明、ソフト食の召し上がり方を説明し、さらにとろみ剤の使用方法をお伝えさせていただきました。
説明をきいていただいたご家族から「だんだんどれがどれかわからなくなってきた」(ほんと、説明している僕もわからくなってきました・・・机の上にも3種類もパンフレットと召し上がり方と申込書類等々が山積み)
「お食事は土曜からご用意しますので、それぞれ温めてとろみ剤使って召上ってください。当日配達の際に配送員からも説明させていただきますから。」とお願いし退席。当日は土曜ということもあり、事前に当日配送担当の方に入念に申し送りをしてお届けしてもらい。お届け後に再度もう一度説明にお電話で確認。
すると最初に食べたTaBeLu+がT様にとって食べやすかったと昼過ぎにご家族から連絡があり。以後健康食のキザミ食は利用無く、ずっとTaBeLu+を昼夕でご利用いただいております(誤嚥やムセもないようです)
バタバタした中で、いろいろな形態の食事を提案させていただきましたが、T様にマッチする形態が見つかってよかったです。歯の治療が終わったら健康食常食にアップしていきたいと思います。

山形に出張にいったときにご馳走になった。山牛さん。
山形で一番の焼き肉屋さんらしいです。美味しかったです。

三角バラは一切れで100kcalあるぐらい脂がのってました。

はーと&はあと 管理栄養士 島田天心