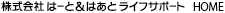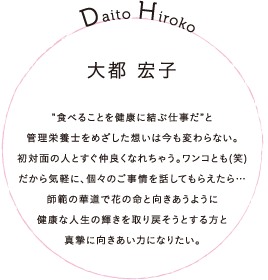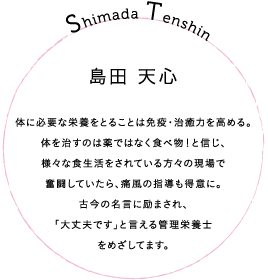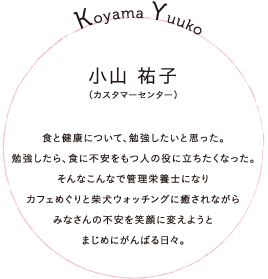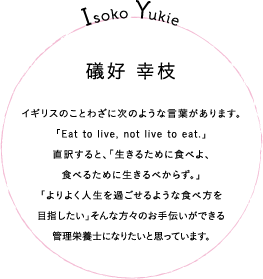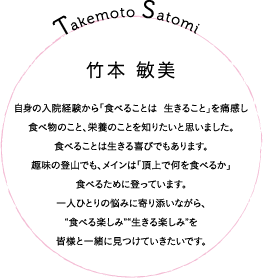こんにちは!管理栄養士の柴田です。
大阪茨木市にデイサービスがオープンして約2週間が経ちました。
無料体験にきていただいたり、契約をしていただくご利用様も増え、
忙しくなってきました!
デイサービスオープンに伴い、クリニックで行っていた栄養指導も
藤本さんに引き継ぐことになりました。
このクリニックでの栄養指導は残りわずかですが、
最後まで精一杯ご指導させていただきます!
今回は、本日クリニックに来られた45歳女性、糖尿病の方です。
医師から初めて血糖が高いと言われて、初めての栄養相談です。
HbA1c8.9、中性脂肪350程度と、血糖コントロール不良。現在服薬はありません。
相談室に入ってくるなり、「私、食生活を変えるのは無理です!」と不機嫌なご様子。
ストレスがあると、すごく食べるんです。いろいろと言われるとそれがストレスになるから食べるのをやめろといわれても無理です、と。
ご家族も糖尿病でインスリンをされているため、糖尿病について知らないわけではない様子。
まずは病状についてお伝えし、合併症の怖さ、日常生活への影響などお話しさせていただきました。
食生活を変えるのは無理!と言っていますが、実はこの方、「食べる順番療法」を実践し、5kg程度痩せたとのこと。
できている所は褒めて、やればできる!という気持ちになっていただくことも大切です。
さて、この方、「私は食べています!」と宣言するほどだったので、改善策はないか、食生活を伺っていくと
夕食後の間食が止まらなく、おやつを2個3個・・・と、ずっと食べてしまい、家に食べるものがないと近くに買いに行ってしまうほどのようです。
ですから、この方には、「夜の間食は、好きなものを一つまで食べてもよい」という目標を立てていただき、1か月間実行するよう約束していただきました。
「よかった、夜の間食は一つなら食べてもよいんですね」とほっとしたご様子。
最初の不機嫌そうな表情も少し和らぎ、笑顔がみられました。
私もひとまず安心です。
食事療養が嫌だとおっしゃる方には、何か一つだけでも、実行できそうな目標を立てていただくようにしています。
糖尿病の病状が悪化するとインスリン治療になったり、合併症である網膜症や神経障害、糖尿病性腎症というQOLに大きく影響する怖い病気です。今回の栄養指導で病気の怖さを知るきっかけ、そして食事療養をスタートするきっかけになっただけでも、この方の第一歩になったのではないでしょうか?
「無理」と言わず、「これならできる」を探すお手伝いをするのも管理栄養士の役割ですね!
クリニックでの栄養指導が終わってしまうのは非常に残念ですが、これからはデイサービスに来てくださる方に何か一つ「あなたに会えてよかった」と言っていただける存在で居られるよう頑張りたいと思います。
デイサービスのホームページもアップされたので、是非ご覧くださいね!
管理栄養士 柴田満里子