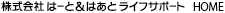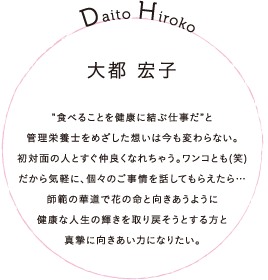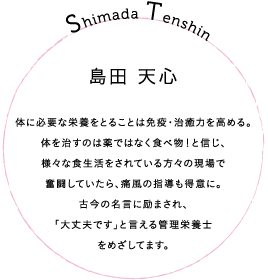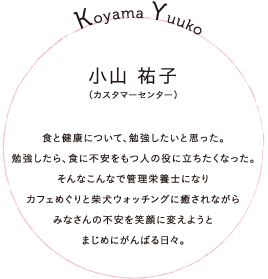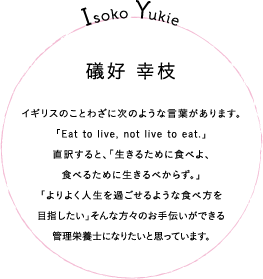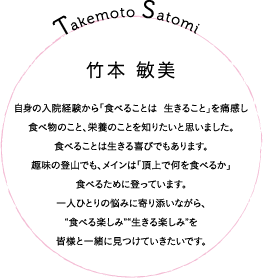こんにちは。
FFS事業部の管理栄養士柴田です。
相変わらず暑い日々が続いていますね!
これは、FFS事業部のセントラルキッチンで働いている従業員の方が
丹精込めて育ててくださったスイカです!
一番立派なスイカを送ってくださったのです。
一人で運ぶのが大変なくらい大きくて、重たい~!
夏といえば、
食事を扱う私たちにとって、十分に注意しなければならないことがあります。
それは、食中毒!!
最近気になる2件の食中毒がありましたね。
一つ目は先日のゲリラ豪雨。
配給物資のおにぎりが原因と考えられる食中毒が発生しています。
原因は黄色ブドウ球菌が生産した毒素。
製造時には問題なかったのですが、保管時に30度程度の所に2時間ほど置かれていたので
その間に毒素を生産したのだと考えられています。
黄色ブドウ球菌は、どこにでも潜在していますが、特に人の手指・傷に多く分布しています。
ですから、手で食品を直接触らないことが重要です。
しかし、調理してすぐ食べる、または10度以下で保管していれば
菌の増殖を抑え、毒素による感染を予防することができます。
温度管理の甘さから生じた事件と考えられます。
またもう一つは、
北海道で生産された浅漬から発生した腸管出血性大腸菌O-157による食中毒。
特に抵抗力の弱い高齢者に感染し、死者も出ています。
こちらは製造先での衛生管理が問題であったといわれています。
予防するためには、食品の十分な加熱、手洗い、消毒が必要ですが
殺菌のための塩素消毒の殺菌効果が不十分だったことが原因と考えられています。
食中毒は、ほんの小さな気の緩みが原因で
多くの人の命を奪いかねません。
食中毒の三大原則は
『つけない』『増やさない』『やっつける』です。
まずは、手洗いを念入りに!
そして、しっかり加熱し、すぐ食べる(常温に食事を放置しない!)
そして片付ける(洗浄・殺菌)。
一つ一つ、自分ができることを実行し、
また周囲の人に呼びかけることで
食中毒から身を守っていきましょう☆
まだまだ暑い日が続きますよ~(^_^)/
管理栄養士 柴田 満里子