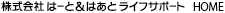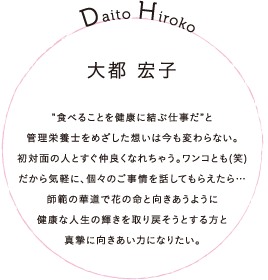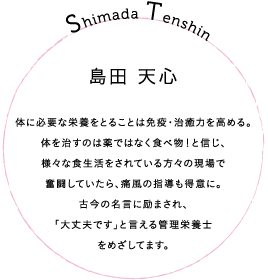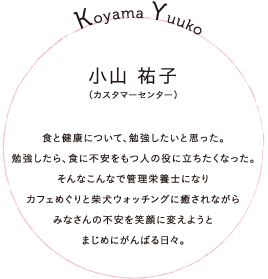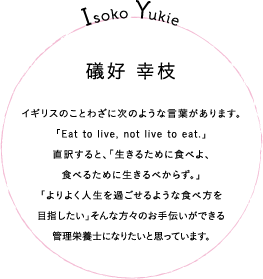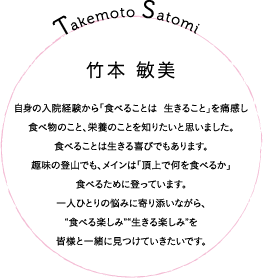めでぃ京都の寺田です。
真夏のような暑い日が続いたかと思えば、
今度は台風が猛威をふるっていますね。
毎日天気予報から目が離せませんっ。
さて今日は、糖尿病をお持ちの努力家のご利用者様の話です。
67歳、男性、前に糖尿病と診断され、入院経験があります。
7年前は77kgでした。
病院からすすめで、
はーとの食事を夕食毎日ご利用を開始されました。
本来であれば、お食事をお届けさせていただく際に
配送員とコミュニケーションをとっていただき、
ご病状の経過を確認していただくのですが、
この方はまだ若く、頻繁に外出するので
お食事のお手渡しではない方法をとらせていただいております。
ですから配送員とも話す機会がほとんどなく、
しかも、電話をしても、不在がちで連絡が取れず、
この方がどのような状況で、どのように過ごされているのか
把握することができていない状況が続いていました。
今年に入り、栄養コントロール食の方には
必ず3か月に1回のフォローをさせていただく方針になったので、
『連絡が取れない』と言っている場合ではなくなりました!!
なんとしても、この方の状況確認と、フォローをしなくては!と思い
自宅へ何度か出向いたり、電話をかけたりを試みてきました。
しばらくはなかなか連絡がつかなかったのですが
今から3か月ほど前、ようやく電話がつながり、お話しすることができたのです。
7年前は77kgだったので、
HbA1cも悪化しているのでは…と予想しながら伺うと、
なんと、現在の体重は58kg!HbA1cは5.8と安定しておりました。
血糖コントロールの服薬は一切ないとのこと。
『すごいですねえ、どのようにすごされてきたのですか?』
と伺うと、
夕食は、はーと&はあとの食事を食べ、
好きだったおやつは一切禁止、
更に雨の日以外はほぼ毎日最低1万歩の散歩する
といった生活を実践し、ずっと継続させてきたというのです。
糖尿病と診断されたことがとてもショックだったのでしょう。
始めの病院での診断時に食事療養と運動の必要性をきちんと理解し、
自分の欲に負けず、がんばってきたのだと話してくださいました。
『これからも継続してくださいね。』
と励ましの声かけをさせていただき、次回フォローの約束をさせていただきました。
それから3か月が経過し、お電話で再びフォロー。
体重とHbA1cを伺うと、
体重は58kgと維持、HbA1cはさらに下がり5.7となったとのこと。
食事も運動もばっちり継続してます!
と嬉しそうに話してくださいました。
主治医の先生からも、
『本当に素晴らしい。7年前、君と同じ状況だった人の半分は再入院したり、合併症を併発して苦しんでいるよ』
と言われ、
ご自身のやっていることは間違っていなかったということを確信し、
とても誇らしく感じておられるようでした。
更に3か月後の目標は、
『運動と食事療養を継続し、配食の頻度を週7回から4回程度まで減らし
自分で用意できるようになる』と決めていただき、
くれぐれも無理はしないことと、風邪をひかないようにと
念を押させていただき、これからの3か月をすごしていただくようお伝えしました。
この方のように、食事療法と運動療法を継続し、
状態を維持されている方は他にも何名かいらっしゃいます。
これは決して簡単なことではありませんが、
このように、努力して結果を出している方がいるということは
他のご利用者様にとっても励みになると思います。
『糖尿病は一生治らないし…』と落ち込んでいる他のご利用者様にも
どんな小さなことでも実践し、継続すれば結果につながるということを
もっともっと伝えていきたいと思いました。
『継続は力なり』
私の好きな言葉です!
はーと&はあと
管理栄養士 寺田満里子