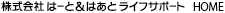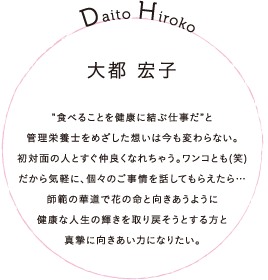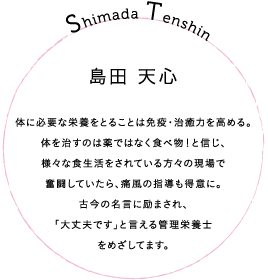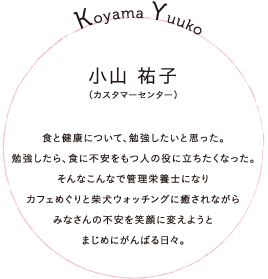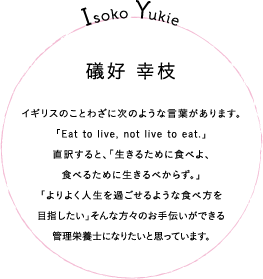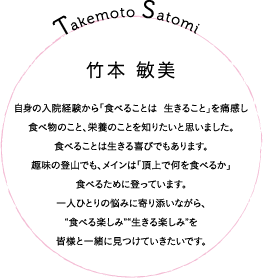こんにちは、京都管理栄養士の松政です。
6月に入り日差し強くなってきました。もう梅雨ですし、
節電の夏、今から暑さに慣れていこうと思います。
余談ですが、先日、ちょっと「お~っ!」と思ったことがありました。
それは、先月の電気代です。1484円でした。なかなかでしょう!
今までの最低を記録しました!
結婚後、「1人暮らしの時と意外と変わらないな~」と思い、最近のエコ家電のすごさを実感していたのですが、冬を過ぎ、暖房などを使わなくなったのと、今月は休日も外出することが多かったためか、こんな結果に。どこまで記録を伸ばせるか頑張ろうと思います。
さて、今月で利用1年になる利用者様。
80歳代、女性、糖尿病性腎症のS様。
S様の話を通し、水分管理の大切さをお伝えしていた方です。
去年の6月、退院後に利用が始まったのですが、秋から冬にかけて入退院を繰り返しておられました。
病院でもなかなか病状が安定せず、何が原因だと先生も首をかしげてしまった方です。
一つの原因は、水分管理、服薬分の水を水分量と入れておらず、水分オーバーに。
あと、食事の残食が多かったことも原因だったと思います。
しかし、年明けに退院されてからは、食事も全量摂取を目指し(娘様が管理)、水分についても気を付けておられます。
その結果、その後の入院はありません。また、Creが2台になり、5月は2.3でした。
体重管理もできてきます。
ちゃんと計算されコントロールをされた食事でも食べていただけないと意味がありません。
特に高齢者の方は体調や精神的なことなどで摂取量が変わることがあります。
S様の場合は好き嫌いだったのですが・・・
そのため食べれていないとなると何が原因なのかを確認することが大切です。
制限よりもまず食べていただくことを優先することもあります。
一緒に原因を探し、しっかり食べていただけるようにサポートしたいです。
管理栄養士が毎回利用者様の所に行き、摂取量を確認することはできないのですが、その代わりに配送員が声かけさせていただきます。
残す量が多くなった場合は一言伝えてください。
より長く在宅で過ごしていただくためには、やっぱり、食事が大切です。
先日ならまちに行ってきました。
あるお酒の蔵元で試飲をさせていただきました。
グラスを購入すると5種類試飲させてもらいました。
おまけに奈良漬試食もできる。
グビグビと飲み、いい気分になりました。
はーと&はあと 管理栄養士 松政千佳子