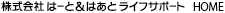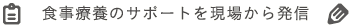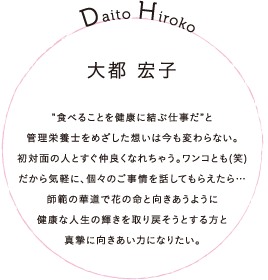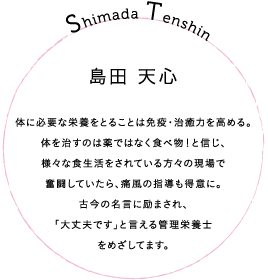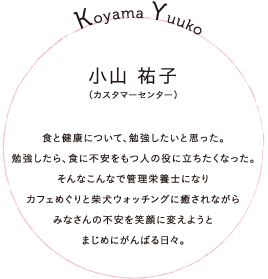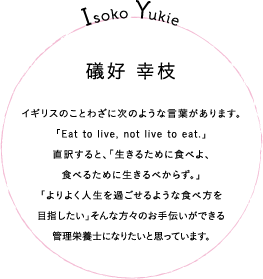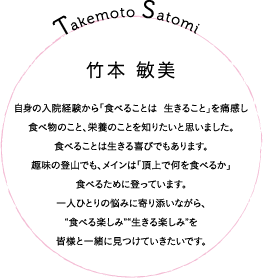こんにちは。管理栄養士の竹本です。
例年より1週間遅れで やっと桜も咲き始めましたね。
バイクで走っていると気持ちいい気候ですが、汗かきの私は服装を間違えると汗だくに...(;^_^A
朝夕はまだ肌寒いので、みなさん体温調節には注意してくださいね。
さて、皆さんは「認知症カフェ」というものをご存じでしょうか?
認知症の方や、その家族、地域住民が気軽に集い、情報交換や相談、
認知症の予防や症状の改善を目指した活動ができる場所です。
先日その認知症カフェで「認知症を予防する食事」というテーマでお話をさせていただく機会がありました。
「これを食べれば認知症にならない」といったスーパーフードのお話ではなく、
今回は認知症のリスクを高める糖尿病や高血圧などの生活習慣病や
フレイル(加齢により心や体が衰えた状態)を予防するための
食事のポイントをメインにお伝えしました。簡単にご紹介します。
【生活習慣病を予防する食事のポイント】
①適正体重(BMI=22)を維持する。
身長(m)×身長(m)×22 が適正体重の目安となります。
②バランスの良い食事を摂る。
主食・主菜・副菜のそろった食事が理想です。
③塩分を控えめにする。
日本人の1日当たりの塩分摂取量は男性で7.5g、女性で6.5gが目標です。
(日本人は1日平均10g取っているそうです(;^_^A)
④野菜をたくさん食べる。
生野菜だと1食あたり両手に1杯分が目安です。
【フレイルを予防する食事のポイント】
☆たんぱく質をしっかり摂る
肉・魚・卵・大豆製品・乳製品のどれかを毎食摂るようにしましょう。
各項目の詳しいポイントはまた次回以降でお伝えできればと思います。
管理栄養士として大勢の方の前でお話するのはほぼ初めてだったので
とても緊張しましたが、みなさんとても真剣に聞いてくださり
京・明日路の無料試食を申し込んでくださった方に後日お会いすると、
「お肉手のひら1枚分食べてるよ」と嬉しいお言葉(#^^#)
認知症だけでなく、様々な疾患の予防につながる基本的なポイントですので
みなさんもどれか一つからでも実践していただけると嬉しいです。
「具体的にどうすれば...」という方は管理栄養士がご訪問しますのでお気軽にご連絡くださいね。
〈TaBeLu+倶楽部 デジタルカタログは下記をクリック〉
https://www810810.meclib.jp/heart810/book/index.html
<カタログをご希望の方は下記から閲覧・ダウンロードできます>
https://www.810810.co.jp/download/
はーと&はあと 管理栄養士 竹本敏美