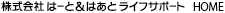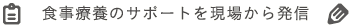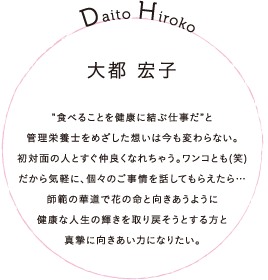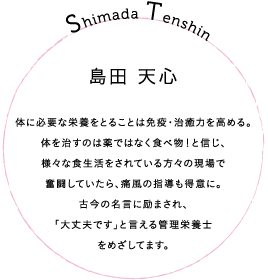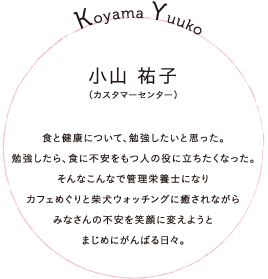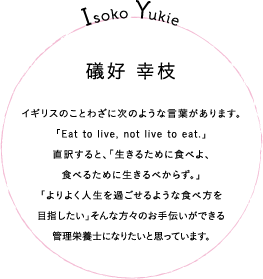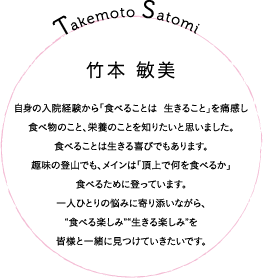皆さんこんにちは、京都管理栄養士の竹輪です(^_^)/
朝晩はまだまだ冷え込んでいますが、昼間は春の陽気になってきましたね!
桜の開花宣言を今か今かと待っています(^o^)
桂川沿いにきれいな花が咲いていましたが、これは桃の木でしょうか(^_^;)?
先日、3月16日(土)に京都市栄養士会主催の『在宅でも役に立つ簡単フィジカルアセスメント』の研修会に参加してきました。
フィジカルアセスメントとは、症状や兆候(兆し)から情報を収集して、必要に応じて触診や聴診を行い、患者さんの状態を把握することでをいいます。
訪問看護の看護師さんが講師となり、在宅へ訪問しアセスメントする際に本人様からヒアリングする内容だけでなく、触れ合ったときの肌や爪の状態・本人様からの訴え以外で状態を把握する方法などを学んできました。
看護師さんたちは訪問時に本人様の訴える症状のほかにも、触診・打診をしながら痛みの箇所を特定したり、聴診をし体の中の確認を行われています。
認知症により自分の症状の訴えが正しくない方も多いので、日々の状態を確認することでその方の異常にいち早く気が付くことが大切なのだと話されていました。
私たち管理栄養士は訪問時に本人様の体に触れたりはしませんが、話を聞くときに話だけに集中せずに、その方の全体に目を向け、話している時に口唇や舌が乾燥していないか、呼吸は荒くなっていないか、手の血管や爪はどのような状態かなど様々なことに意識を向けながら、その方の現状を把握していくことが大切なのだと思いました。
はーと&はあと 京都管理栄養士 竹輪美里